|
「申し訳ありませんが、保証書は登記義務者に間違いが無いことを保証するものですから本人を確認しなければ作成する訳には行かないのですよ」 田依は少し冷たいかなと思ってはみたが事は保証書に関する事だけに厳格に取り扱わなければいけないと自分に言い聞かせるのであった。それではなくても女性に対する態度が非常に甘くなる性癖を彼自身十分に認識していたのでここは少し厳格になる方が良いと更に自分に言い聞かせるのであった。 「先生のおっしゃることは良く分かりますが、何せ今日どうしてもお金が入用なんです。夫は出張して連絡がとれませんが、その辺の事情は長崎の姉が詳しく知っていますので電話して頂けないでしょうか」なおも執拗に言ってくる女性から醸し出される甘い香りに田依は男としての本能をくすぐられるような感覚を抱くのであった。 <ここで引き受けてやればきっとこの女性は喜ぶだろうな> 男として女性の喜ぶ姿を見るのは悪いことではない。相手が美人であれば尚更のことである。 彼の心の中に女性の味方になってあげたいと云う男気(世間一般には助平心とも云うが)が少しづつ湧き出して来ている。 |
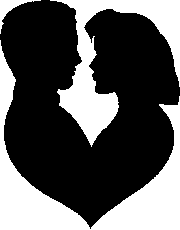
|
田依は困惑しながらも逡巡した。先ほどから女性の話を聞くかぎりではどうも嘘ではなさそうだ。 <長崎に電話をしてみるか>しかし電話をしたところで、本人と話せる訳ではないし、反って電話をしたが為に断わるのが難しくなるかも知れない。彼は大いに悩んだ。
田依がオーケーを出せばすぐにでも金を出すと金融業者は言っている。この女を信じて保証書を作ってやるか。田依はここまで考えた時、過去において彼が散々女性から騙されたときの事が思い浮かんできた。 彼を騙した女性と云ってもその殆どが飲み屋の所謂水商売の女性達であった。 しかし、彼女たちは極端に云えば男を騙すのが商売であって、男はそうと分かっていて騙される場合もあれば、完ぺきにだまされる場合もあるのであった。 何れの場合もその種の女性たちのだましのテクニックは如何にも気があるようにふるまい時には哀調を交え男の冷静さを忘却させるように行うのであった。 田依も今までに幾度となく彼女等の甘い毒牙にかかってきたが、それは彼の女性に対する愛の深さから来ているものと納得し、彼自身彼女等を恨んでなんかはこれっぽちもなかったのである。 「先生、もう先生しか頼るところがありません。どうかお願いします。先生には絶対ご迷惑をおかけいたしませんから。どうか人を助けると思って引き受けて下さいませんかお願いします。」 女性は哀願するように言った。女性の白い手にはダイヤの指輪が輝いている。その細く白い手に実印を入れているのであろう印鑑ケースが収まっている。 2/3 |

